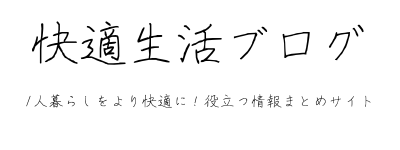自炊をしていると、よく悩むのが生ごみの捨て方。
この生ごみの処理を怠ったり、間違えたりすると不快な悪臭や害虫の発生の原因になります。
悪臭や害虫が発生するのは嫌だけど、その生ごみの捨て方がわからないと悩まれる方が多くいらっしゃいます。
筆者も生ごみの捨て方を間違えてコバエに悩まされたことがあります。
この記事では、生ごみの捨て方の基本的な知識から具体的な方法、捨てる際の注意点などの詳細を解説します。
記事を読んで自炊を楽しんでいきましょう。
- 自炊をこれから始めるかた
- 生ごみの捨て方に悩んでいる方
- 自炊をよくする方
生ごみだけでなく、生活の中で出てくるごみの分別方法などに悩んでいる方はぜひこちらの記事もご覧ください。
「【解説】ごみ分別の基本的なルールとごみの分別する重要性をお教えします!」
「【徹底解説】タレがついた袋は何ごみ?正しい分別方法と処理のコツ」
生ごみの種類と特性
生ごみとは、私たちの日常生活から出る有機物の廃棄物を指します。
自炊をしていると、野菜の皮や肉の破片など料理に不要な部分が出てきます。具体的には、食品の残り物や皮、種、葉っぱなどを含みます。
これらの生ごみは性質上、非常に腐りやすく、適切に処理しないとすぐ悪臭や害虫を引き起こします。ここでは、生ごみの具体的な分類とその特性、さらに各種生ごみの処理方法について詳しく解説します。
生ごみの分類
生ごみは、大きく分けて「生鮮食品類」、「調理廃棄物」、「食べ残し」の3つに分類されます。
生鮮食品類は、果物や野菜、その皮などが含まれます。
調理廃棄物は、料理の過程で出る皮やヘタ、また調味料が残ったものを含みます。
食べ残しは、実際にお皿から残された食品を指し、食卓に並んだ時点での新鮮さが失われていることがあります。
また、これらの生ごみはそれぞれの状態によって水分量や栄養成分が異なり、その特性や処理方法にも影響を与えます。
それぞれの生ごみの処理方法
生ごみの処理方法は、その種類によって適切な処理方法が異なります。
まずは、それぞれの生ごみの種類について解説します。
例えば、生鮮食品類や食べ残しは微生物の分解能力を利用して肥料として再利用できるメリットがあるが、有機物の分解速度が遅く、悪臭が発生しやすいという特性があります。これに対して、調理廃棄物は料理の過程で水分が多く含まれることから腐りやすいため、速やかに処理することが重要です。
生ごみ処理方法について、基本的には可燃ごみとして処理されることが一般的です。
一方で、家庭内のコンポストや堆肥化を通じて土に還す方法もあります。
※コンポストとは、生ごみや落ち葉などの有機物を微生物の力で分解し、堆肥に変えるための容器、またはその堆肥そのものを指します。
各タイプの生ごみにはそれぞれ異なる処理方法があり、専用の容器を用いること、または発酵促進剤を加えることで効率よく処理することが可能です。
また、近年増えているのが「生ごみ処理機」の活用です。これは、生ごみを微細化し、発酵させる機能を持ち、家庭内での生ごみ処理を大幅に簡素化させる製品です。生ごみ処理機により、処理の手間や悪臭の問題を軽減することができます。しかし、どの方法を選ぶかは家庭の状況や生活スタイルに合わせて選択する必要があります。
処理後は適切な方法で堆肥を作り、庭やプランターに利用することで、資源の再利用が実現します。生ごみの処理は、ただ単に廃棄物を処理するのではなく、環境への貢献にもつながる重要な活動であることを理解することが重要です。
生ごみを捨てずに放置してしまうと…

生ごみを捨てることは、私たちの生活を快適に過ごすために非常に重要な役割を果たしています。
もし生ごみを捨てずに放置した場合は、以下のようなことが起こる可能性があります。
①悪臭の発生
生ごみを放置すると、腐敗臭といった嫌な臭いが発生します。
この生ごみの臭いの原因は雑菌やカビの繁殖によるものです。この雑菌やカビは、生ごみを餌にして水分が豊富で温度が高くなると、より活発に繁殖するといわれています。それらが、生ごみを分解しようとして腐敗していき悪臭に変わります。
特に湿気の多い梅雨や気温が高くなる夏の時期は注意が必要です。
②害虫の発生
生ごみを放置すると、ハエやゴキブリなどの害虫や場所によってはネズミなども発生する可能性があります。
発生の原因としては、玄関や窓、排水溝などあらゆるところから侵入してきた害虫が、生ごみを好んで集まる傾向にあります。数日放置しただけでコバエが発生しますし、長時間放置してしまうと、コバエが生ごみに卵を産み、大量発生してしまいます。
③病原菌の発生
生ごみを放置すると、雑菌やカビの繁殖と害虫の発生が起こる可能性があります。
カビが生ごみに発生してから時間が経つと、カビがキッチン内で繁殖しカビの胞子が空気中に拡散されてしまいます。その胞子が体内に侵入すると、食中毒や肺炎などの病気にかかる可能性があります。
また、発生した害虫によっては、食中毒などを引き起こす病原体を保有するものもいるので、病原菌の発生源になることがあります。
つまり生ごみを放置してしまうと、悪臭や病原菌の原因となるので、定期的に生ごみを適切に捨てることが大切です。
実践的な生ごみの上手な捨て方
生ごみが実際に出てしまった場合、どうやって捨てるのかいくつか方法をご紹介します。
生活の状況によって捨て方が変わるので、自分の環境に適した捨て方を見つけて、すぐにでも実践できるようにしていきましょう。
可燃ごみに捨てる場合
一般的に生ごみが出たら可燃ごみに出すこと多いです。
生ごみが出たらそのまま直接ごみ袋に入れてしまうと、悪臭や害虫が発生してしまいますので、ごみ袋に入れる前に捨て方のポイントがあります。
①新聞紙を使う
新聞紙は繊維に隙間が多く、水分を抜くには効果的な素材のため吸水性に優れており、生ごみの水気を吸い取ります。
新聞紙で包むと生ごみの水分が抜け、臭いが出るのを軽減できます。また、新聞紙で使用されているインクには炭が含まれているため、消臭効果で悪臭も軽減できます。
新聞紙がない場合、代替品としてキッチンペーパーで水分を取ることもできます。
②水切り器を使う
生ごみの約80%は水分が含まれていると言われています。
この水分が放置されると悪臭の原因になってしまいます。毎回新聞紙やキッチンペーパーを使用するとごみが増えて環境にもよくないので、水切り器を使うことも良い方法です。
三角ネットに置いておくだけだと、水分は抜けないので、捨てる前に水切り器で水分を抜くと良いでしょう。
③天日干し
生ごみを天気の良い日に天日干しすると水分が蒸発します。数日間放置すると水分が抜け、質量が減るのと悪臭の防止ができます。
ただし、天日干しをする際は注意が必要です。衛生面に配慮せずに外に放置すると、近所に悪臭や害虫で迷惑をかけてしまうので、天日干しのやり方には注意しましょう。
④重曹・クエン酸を使う
すでに生ごみから腐敗臭がし始めたら、重曹かクエン酸を使うと悪臭を軽減できます。
食材が酸化した臭いである腐敗臭は酸性で重曹はアルカリ性なので、重曹を使うことで生ごみの酸性を中和させることが可能です。
クエン酸は酸性ですが、生ゴミからアンモニア臭が出ていれば、アンモニア臭はアルカリ性なので、クエン酸で中和できます。また、クエン酸は殺菌効果ぎあります。
使い方としては、生ごみに直接かけるか重曹水(もしくはクエン酸水)をスプレーボトルに入れて吹きかけるのが有効です。重曹水は水100mlに対して重曹小さじ1杯で作れます。クエン酸水は水100mlに対して小さじ1/2杯で作れます。
⑤冷凍する
悪臭や害虫問題の解決策として、冷凍することも1つの手段です。例えば、何かしらの事情により長時間生ごみの処理ができないときに有効です。
生ごみが発生したらすぐに密閉袋に入れて冷凍庫に入れます。細菌の多くが冷凍庫の温度では増殖できないため、冷凍庫で凍らせれば菌の増殖を抑えて腐敗を遅らせることができます。
その結果、悪臭や害虫の発生を防ぐことができます。
生ごみを冷凍する際は、臭い移りや細菌が繁殖しないように密閉袋に入れることをおすすめします。
⑥お菓子袋に入れる
お菓子袋は生ごみの臭いを防ぐのに有効です。
お菓子袋は空気が通り抜けにくく、臭いが蔓延するのを軽減することができます。
お菓子袋一枚だけでは心配な人は、二重にして入れると良いでしょう。
⑦塩を使う
生ごみの水分を抜くのに塩を使うのが有効です。
塩は浸透圧により脱水作用があります。生ごみに直接塩をかけることで水分を抜くことができ、生ごみの腐敗を遅らせることができます。
⑧蓋つきの密閉ごみ箱を使う
生ごみを保管する場所に困ったら、蓋つきの密閉できるごみ箱を使うことをおすすめします。
蓋つきのごみ箱を使えば、収集日まで部屋中に臭いが漂うのを予防できます。
ごみ箱を使っていると内側が汚れたり、放置するとカビが生えやすくなったりするため、定期的に汚れを拭い消毒をしましょう。
⑨ごみ処理機を購入する
ごみの保管が手間に感じる人はごみ処理機を使うのもいいでしょう。
生ごみに含まれる水分を熱で乾燥させることで、除菌・脱臭が可能です。
ごみ処理機は大きく分けて乾燥式とバイオ式の2種類があります。
乾燥式のメリットは、室内に置けて価格が手頃なことです。ただし、作業中に臭いと音が発生するほか、電気代は高くなる傾向があります。
バイオ式は音が静かで、電気代は比較的安価です。ただし、臭いが発生するうえに、屋外にしか設置できないです。
自分の生活スタイルに合ったごみ処理機を選ぶようにしましょう。
コンポスト化する場合
コンポスト化は、生ごみを微生物の力で分解し、栄養豊富な堆肥を作り出す方法です。
この方法を利用することで、家庭から出る生ごみを無駄にすることなく、有効活用することができます。コンポストは特に、生ごみの処理と堆肥を作成を同時にできて土作りや植物育成に役立つため、ガーデニングや家庭菜園を行う方にとってはおすすめの方法です。
コンポスト化の手順は主に以下のステップからなります。
まず、生ごみを集めます。野菜や果物の皮、コーヒーかす、卵の殻などはコンポストに適していますが、肉類や油分の多い食品、乳製品は避けるべきです。
次に、集めた生ごみを通気性の良い容器に入れるか、直接庭に堆積します。ここで重要なのは、通気性を確保するあために、堆肥の層を形成するときに、乾燥した落ち葉や小枝などの炭素素材と交互に重ねることです。
このようにスイッチすることで、微生物が効果的に活動できる環境を整えます。
さらに、定期的にかき混ぜることも大切です。酸素を供給することで、分解プロセスが活性化し、臭いの発生を抑えることができます。数ヶ月後には、黒土のような質感の堆肥が完成します。
コンポストや堆肥作りを行う際には、炭や木のチップを混ぜることで通気性を保ち、悪臭の原因となる嫌気性の分解を防ぐことができます。定期的に混ぜることも重要です。さらには、例えば「虫除け」効果が期待できるハーブを用意し、そこに生ごみを置くことで臭いの発生を抑えることも一つの方法です。
完成した堆肥は、家庭菜園に施肥することで、植物へ不足している栄養分を補うことができ、強い植物を育てる助けとなります。
コンポストについて詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
・LFCコンポスト(https://lfc-compost.jp/)
発酵処理する場合
発酵処理は、コンポスト化とは異なり、特定の微生物を使用して生ごみを短期間で分解する方法です。この方法では、 嫌気的条件を利用し、嫌気性の微生物が生ごみを分解します。
嫌気性とは、微生物がエネルギー代謝を行う際に酸素を必要としない性質や状態のことです。
この発酵処理の利点は、速やかに処理が可能なことと、悪臭を抑えられることです。
発酵処理を行う際には、まず適切な容器を用意します。密閉できる容器や専用の発酵装置を使います。容器に生ごみを入れ、その中に発酵促進剤を加えます。これは、米ぬかや酵母といった微生物が豊富なものが一般的です。
この処理法では、水分量が重要であるため、調整しながら材料を混ぜることがコツです。
また、発酵温度を適切に保つことがポイントです。温度が高すぎると微生物が死んでしまうリスクがあるため、30~40度に保つのが理想です。数週間で発酵が進み、元の生ごみは減少し、栄養価のある液体肥料や土壌改良剤として使用できます。
さらに、発生した液体を植物に与えることもでき、育成効果を高めます。液体は薄めて使用することが推奨され、過剰な肥料分の供給を防ぐことができます。
このように、コンポスト化と発酵処理はそれぞれの特徴を活かした生ごみ処理方法です。
どちらを選ぶかは家庭のライフスタイルやニーズによりますが、どちらも環境保護と資源の有効活用に役立つ重要な手段です。生ごみ処理を通じて、より持続可能な生活を送りましょう。
生ごみを捨てる際に注意すること
生ごみを捨てる際に普段から注意しておくと良いことがあります。
それは生ごみを溜めないことです。
上記でもお伝えした通り、生ごみを放置すると悪臭と害虫が発生します。
臭い・虫が気になり始めたら、それは生ごみを溜めすぎてるサインになります。生ごみは面倒くさがらずにその都度、捨てることが大切です。
特に三角コーナーを使ってる人は、放置しがちになることが多いです。シンク内は水気も多い場所のため、悪臭の発生が早くなります。早めに捨てることを心がけましょう。
生ごみを捨てるための便利グッズ
生ごみ処理は家庭でのごみ削減だけでなく、環境保護にも寄与する重要な活動です。
このプロセスを効果的に行うためには、適切なツールやグッズの活用が欠かせません。
ここでは、具体的な生ゴミ処理の便利グッズとして、ごみ処理機とコンポスト容器の選び方について詳しく紹介します。
ごみ処理機の活用
ごみ処理機は、生ごみを手軽に処理できる便利な家電製品です。
近年、家庭での生ごみ処理に対する意識が高まる中、さまざまなタイプのごみ処理機が登場しています。これらの機械は、食品残渣を微細化したり、発酵させて堆肥化することが可能です。特に、乾燥型のごみ処理機は、生ごみを90%以上の水分を取り除くことができ、非常に効率的です。
ごみ処理機には、電気を使わないものから電動式のものまで様々な種類があります。電動タイプは、処理が迅速で、忙しい主婦や一人暮らしの方に人気です。一方で、電球などの光を使って臭いを発生させない非電動式の機器も存在します。選ぶ際には、処理能力やサイズ、音の大きさなど自宅の環境に合ったものを選ぶことが重要です。
例えば、家庭の広さや頻繁に出る生ごみの量を考慮して、適切なサイズのごみ処理機を選びましょう。小さなお子さんがいる家庭では、防臭機能や電源管理ができる機種を考慮するのも良いでしょう。また、処理後の再利用方法も考え、堆肥として活用できるものや、資源ごみに出せるものなど、多機能なごみ処理機も存在します。
コンポスト容器の選び方
コンポスト化は生ごみ処理の一つの方法で、家庭で手軽に行える環境に優しい選択肢です。
コンポスト容器の選び方は、成功するコンポスト作りのカギとなります。
まず、サイズですが、家庭の生ごみの量に応じた適切なサイズを選ぶことが大切です。特に、家庭の人数や食習慣(生鮮食品が多い家庭など)によって、大きさは異なります。
材質も考慮すべきポイントです。プラスチック製のコンポスト容器は軽量で持ち運びが簡単ですが、一方で通気性があまり良くない場合があります。そのため、通気性の高い木製や金属製の容器も考えたいところです。また、遮光性のある容器はコンポスト素材の温度を調整するのに役立ち、効果的な発酵・腐敗を促します。
さらに、フタの有無も重要なポイントです。害虫や臭いを防ぐためにしっかりとしたフタがついているものを選択することが望ましいでしょう。特に都市部では、昆虫や小動物の侵入を防ぐことが重要です。また、位置を定めることも重要です。風通しが良く、直射日光が当たらない場所が理想的です。
最後に、コンポスト容器からの取り出しやすさも考慮しましょう。生ごみがしっかりと発酵した状態で取り出せることが、スムーズなコンポスト利用に繋がります。そのため、開口部が広く、容器内のかき混ぜがしやすいものが望ましいです。このように、コンポスト容器を選ぶ際は多くの要素を考慮し、最適なものを見つけることが成功のカギと思います。
生ごみを捨てる際のポイント
生ごみの適切な処理は、環境保護や資源循環の観点からも非常に重要な課題です。
生ごみの適切な捨て方を知ることで、家庭から出る廃棄物を減少させ、悪臭や病害虫の発生を防ぎます。それを実現するためには、知識や技術が必要ですが、その中でも特に「仕分けのコツ」と「収集頻度の管理」が重要なポイントとなります。ここでは、それぞれの観点から効果的な方法を考えていきましょう。
仕分けのコツ
生ごみを適切に捨てるための第一歩は、適切な仕分けから始まります。
生ごみには野菜くずや果物の皮、魚や肉の残り物、卵殻など、さまざまな種類がありますが、すべてを一緒に処理するのは非効率的です。仕分けを行うことで、コンポストや堆肥化の際の発酵プロセスをスムーズにすることができます。
また、可燃ごみや不燃ごみと混ざらないように、見た目や性質で分けることも重要です。例えば、野菜くずはもちろんコンポストに適していますが、油分の多い食材は避けるべきです。
具体的な仕分けのコツとしては、日々の調理で出るごみを「湿ったごみ」と「乾いたごみ」に分けることが挙げられます。湿ったごみは即座に処理し、乾いたごみは後日まとめて処分するという流れが理想的です。また、食材のパッケージや調理器具のごみも忘れずに分別しなければなりません。自宅に複数のごみ入れを用意することで、少しでも仕分けを楽にすることが可能です。
収集頻度の管理
生ごみの収集頻度は、家庭のライフスタイルや食生活に密接に関連しています。
毎日少しずつ出る家庭では、生ごみの収集頻度を高める必要がありますが、逆に食材をまとめて購入し、長期間保存する家庭では、収集頻度を下げても問題ありません。しかし、いずれにせよ生ごみを放置することは避けなければなりません。放置すると、悪臭や雑菌の繁殖につながり、家庭内の衛生が損なわれる原因となります。
収集頻度を管理するポイントとして、まずは生ごみをまとめて処理する曜日を決め、その日まで持ちこたえることが重要です。各家庭でカレンダーを利用して、収集日を設定したり、忘れないようにリマインダーを設定することも有効です。また、収集頻度を増やす際には、地域でのごみ出しのルールも確認し、他の家庭と協力して効率よく収集の日を設けることができれば、地域全体のごみ処理のペースを改善することにもつながります。
このように、生ごみ処理においては「仕分けのコツ」と「収集頻度の管理」が極めて重要です。毎日の努力が積み重なって、環境への負荷を軽減し、持続可能な生活を実現することができます。家庭全体で取り組む意識同士の連携が、生ごみ問題を解決する大きな力となるのです。
よくある質問とトラブルシューティング
生ごみの捨て方に関連するよくある質問や発生しやすいトラブルについて理解することは、効果的に生ごみを捨てるために重要です。
雑菌の問題と安全な捨て方
生ごみを捨てる際の大きな懸念は雑菌の問題です。
特に、腐敗した生ごみは病原菌や有害な微生物を引き寄せてしまう可能性があります。これを放置すると、健康に影響を及ぼすリスクが高まります。従って、安全な捨て方を講じることが求められます。
生ごみを扱う際には、手指の清潔を保つことが基本です。
具体的には、捨てる前に手を洗い、捨てた後も手を洗うことが重要です。また、生ごみを捨てる際には、専用のごみ袋や桶を使用し、定期的に洗浄を行うことも大切です。これにより、雑菌の繁殖を抑えられます。
また、発酵処理や堆肥化の際にも、しっかりと管理することで雑菌の問題を軽減できます。適度な湿度や温度を維持し、酸素を供給することで、悪臭のもととなる嫌気性の逆転を防ぎながら、健康的な微生物の活動を促すことができます。さらに、完成した堆肥を使用する際には、十分に熟成させることが重要です。これにより、病原菌を減少させ、安全な土壌改良材として利用可能になります。
これらの対策を行うことで、効果的に生ごみを処理し、悪臭や雑菌の問題を防ぐことができます。生ごみ処理に関する知識を深め、正しい行動を心がけることで、快適な生活環境を保つことができるでしょう。
まとめ
生ごみの適切な捨て方を知ることは、快適な生活環境を維持するだけでなく、悪臭や害虫、病原菌の発生を防ぐうえでも非常に重要です。
新聞紙や水切り器、重曹・クエン酸などを活用する工夫から、ごみ処理機やコンポスト、発酵処理といった本格的な方法まで、自分のライフスタイルに合った処理方法を選ぶことで、より衛生的で環境に優しい暮らしを実現できます。こまめな処理と正しい知識が、持続可能な生活の第一歩になります。
これから皆様も生ごみを捨てる際にぜひ参考にしてみてください。